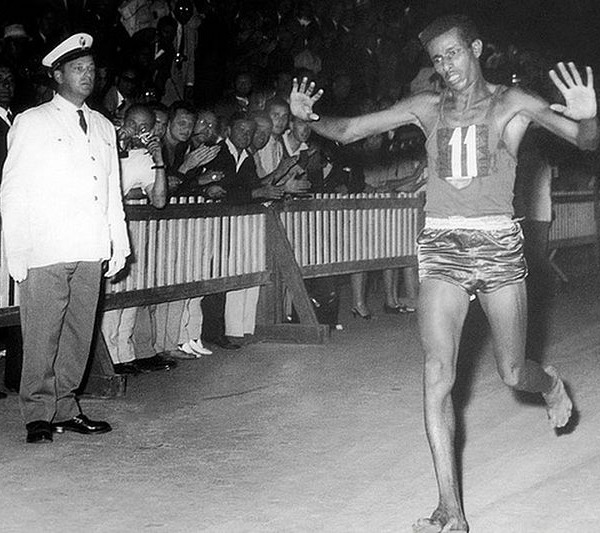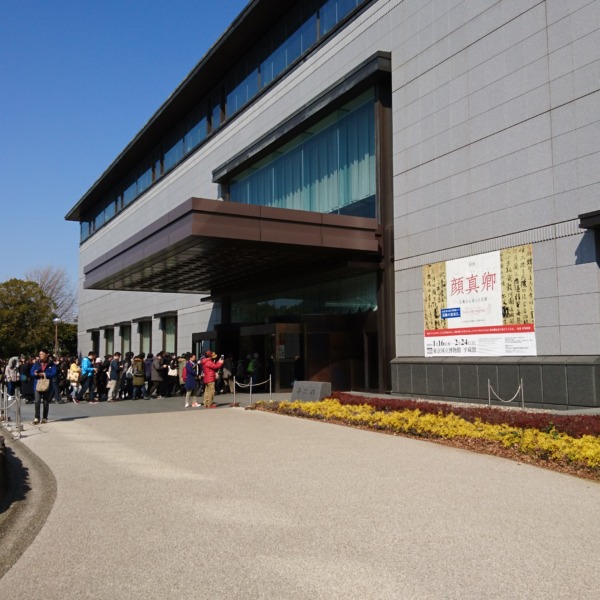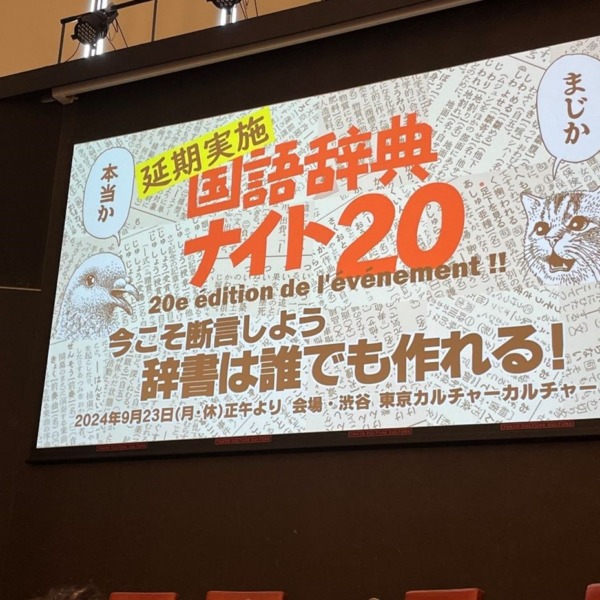1981年夏。大学は出たけれど、自分は何になりたいのかという明確なビジョンがなかった。そんな人材を採用する企業はなく、臨時職員として働くことにした。今は「恵比寿ガーデンプレイス」になっている東京・恵比寿のビール工場の一角が職場だった。
昼休みには、工場の冷たい床にビニールシートを敷いて疲れた体を横たえる。作業ズボンの大きなポケットから小さく折りたたんだ新聞を取り出し、むさぼるように読んだ。愛読紙は毎日新聞。この年5月18日朝刊に掲載された「ライシャワー元駐日大使の核持ち込み発言」(81年度新聞協会賞受賞)をはじめ、79年度の「『ワカタケル(雄略天皇)銘解読』のスクープ」、80年度の「『早大商学部入試問題漏えい事件』のスクープ」と、3年連続で新聞協会賞を受賞することになる毎日新聞の勢いと論調は、心にしみいるようだった。
そしてこの時、私は誤りが浮き出て見えるという感覚を初めて味わった。せっかくの面白い記事なのにどうしたことだろう。当時の日記に記されているだけでも「山口県美弥市」「気慨に満ちた人」「広右募集中」「未来を想像せねばならないとという主張」……。私が探していた仕事はこれだ!と気づくまで、さして時間はかからなかった。
以来、校閲の仕事は生活に役立つというより、生活そのものとして一緒に人生を歩み続けることになる。それにしても、当時の活版印刷から現在のコンピューター制作に至るまで、誤りの種類はほとんど変わっていないことに驚かされる。活字を手で拾っていた時代特有の「広右(告)」は別にしても、「山口県美祢市」「気概」「創造、ならないという」などの例は、最近でも珍しいことではない。
ここに、新入社員研修を終えるにあたり先生役の先輩記者からいただいた一枚の色紙がある。
「謙虚な目で見て、新鮮な感覚でとらえていくと、普段見逃しているものが見えてくる。見えてきたことによって、別に秘密文書をとらなくても、新聞にいのちを吹き込むことができる。校閲とはそんな仕事ではないか」
もう何十年も誤りは浮き出て見えないし、こんなかっこいいことをさらっと書く人にはなれなかったけれど、ひたすら間違い探しをしていたあの夏の日。目をとじれば「サッポロ」の抜けるような青空が、今でも私の校閲人生を応援してくれているかのようだ。
【渡辺静晴】