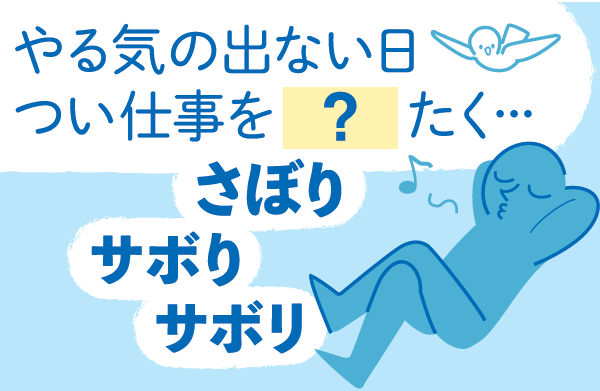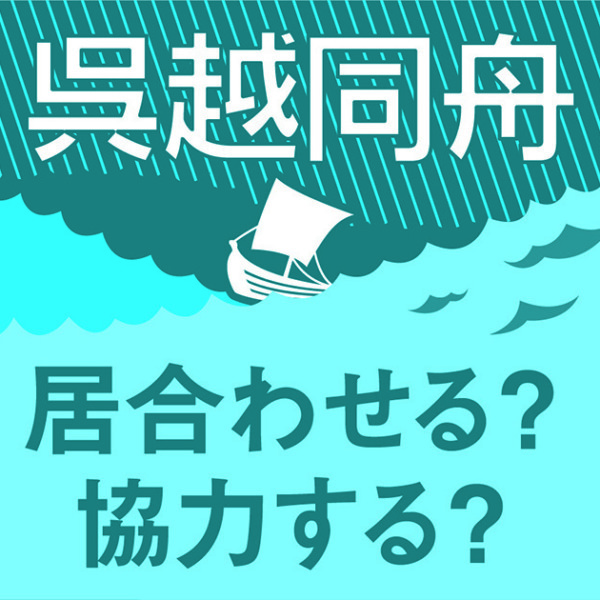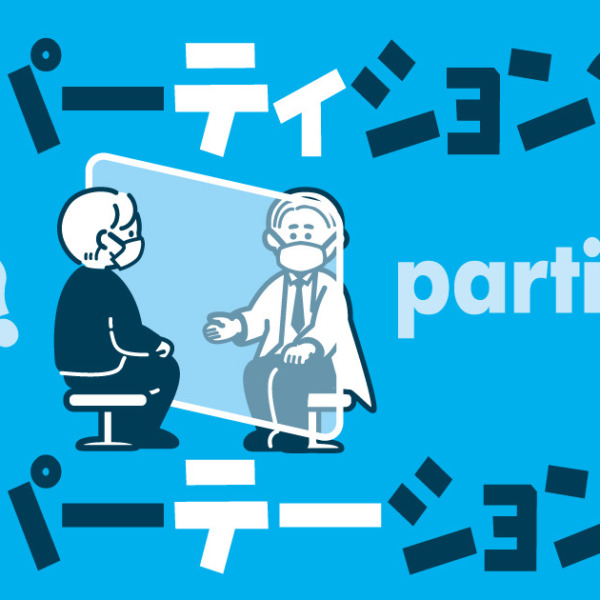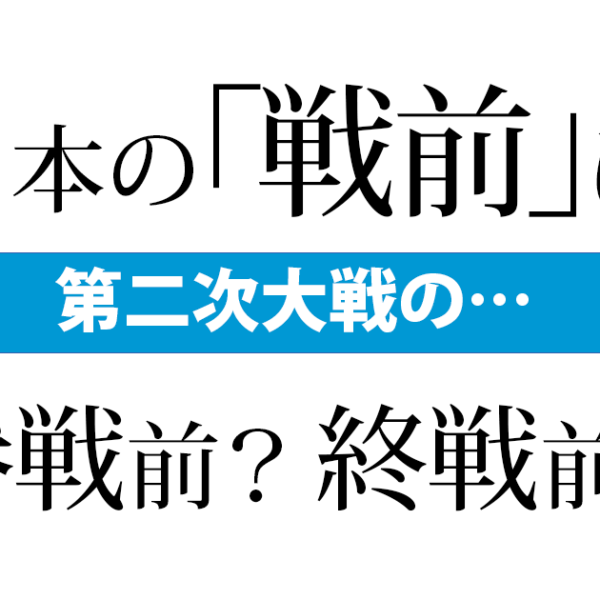「縁日」の使い方について伺いました。
目次
8割は「市」のこととして使うが…
| 「縁日」という言葉を「露店などが集まる市」のこととして使いますか? |
| 使う。他の用法は思いつかない 21% |
| 使う。本来は市のことではないが、許容できる 20.1% |
| 使う。ただし、神仏にゆかりのあるものに限る 37.9% |
| 使わない。縁日は神仏の祭礼などのある日のことである 21% |
縁日を「露店が集まる市」のこととして使う人は全体のほぼ8割を占めました。ただし、そのうちのほぼ半分は「神仏にゆかりのあるものに限る」を選んでおり、露店などが並んでいれば無条件に「縁日」と呼ぶ人は4割程度にとどまりました。
日付も市も指す「縁日」
「縁日」という言葉がどう使われていたのか、少し古い文章で見てみましょう。
銀座の縁日といえば七日、十八日、二十九日と十日毎に一日ずつ出世する出世地蔵が有名である。昔は銀座四丁目の角から三十間堀の方へずらりと出たもので私はぶどう餅が大の好物でそれも亥之助のでないといけないなどと通をふり廻したものである。
(岸田劉生「新古細句銀座通」)
「縁日」とはまず日付のこと。毎月何日、ということもあれば、例えば摩利支天の縁日のように十二支の「亥(い)の日」などということもあります。かつては「●日だから○○様の縁日だ」といったことが生活の一部を占めており、今よりもさまざまな点で神仏が身近であったことがうかがえます。
とはいえこの短い文でも分かるように「三十間堀の方へずらりと出た」というのは縁日の市の出店のことを指しています。「縁日」は神仏にゆかりのある日付のことだと踏まえた上で、その日に立つ市についても「縁日」と呼ぶことに違和感はなかったとみられます。
出世地蔵の縁日は大変なにぎわいであったと伝わりますが、現在は銀座三越の9F屋上に安置されています。縁日にも露店は並びません。

神仏なしの「祭り」と同じか
新聞記事でも「縁日」はだいぶ広い意味で使われています。「縁日や飲食を楽しめるイベントが開かれた。……射的や輪投げなどの縁日でお祭り気分を演出」という具合に、神仏と関係のないイベントであっても、縁日の露店で並ぶような店が出ていれば「縁日」と呼ぶような印象を受けます。
もっとも「祭り」という言葉にしても本来は神仏を祭ることを意味していましたが、今では「記念・祝賀・宣伝などのために行なう集団的行事」(日本国語大辞典2版)として、イベントの類いをも指す言葉になりました。同様に「縁日」も神仏を離れ、「縁日の市のようなもの」を指しても使われるようになったのかもしれません。
言い回しには工夫がほしい
ただし、今回のアンケートでも見たように、露店が並んでいれば何でも「縁日」と呼んでよいと感じる人ばかりではありません。射的だの綿あめだのが出ていれば「縁日」だというのは、言葉の使い方として安易に見えるという意識は必要ではないでしょうか。はっきり「縁日」と言い切るのではなく、「縁日風のイベント」「縁日風の演出」など言い回しを考える余地があるのではないかと思います。
(2025年03月24日)
「縁日」は大辞林(4版)を引くと「有縁(うえん)の日の意」とあり「特定の神仏に縁のある日。その日に参詣すると、特別な功徳があるという」と説明されます。あくまでも「日」を指す言葉で、たとえば毎月10日は金刀比羅宮の縁日です。
辞書の説明には続けて「参詣人相手に市が開かれることも多い」とあります。縁日というと露店の集まる様子を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、あれは「縁日の市」であって、縁日そのものではないということになります。
もっとも、「縁日」で「縁日の市」を指したっていい、一種の換喩(メトニミー)だ、という立場があってもおかしくはないと思います。ただ、「イベントで縁日を企画」のような文言を目にすると「神仏なしに縁日を企画?」と戸惑いを感じることも。「縁日」は既に神仏を離れたものとなったのか、こちらで伺ってみました。
(2025年03月10日)