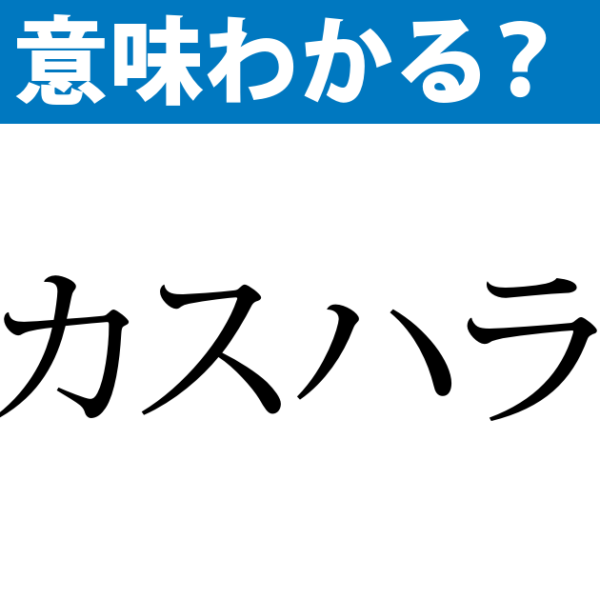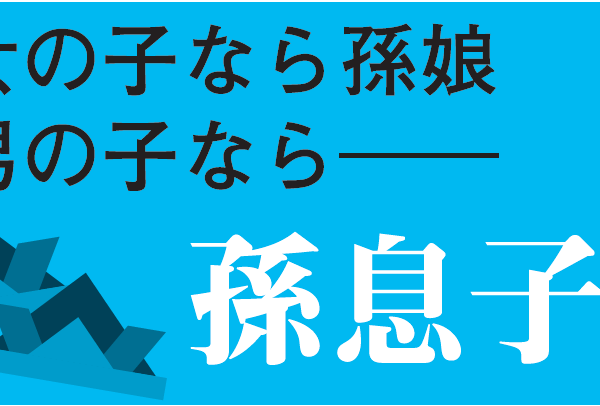「たわわに実る」という言い回しを使う収穫物はどれがふさわしいか、お聞きしました。
目次
「柿」のみで半数超す
| 「たわわに実る」と使えるのは例えば? |
| 柿 54.8% |
| 柿や稲 31.8% |
| 柿や稲や落花生 13.4% |
結果は「柿」「柿や稲」「柿や稲や落花生」の順に多くなりました。「柿」のみが半数以上で、稲や落花生にも使えるとする人は少数のようです。
使用作物が拡大中
質問のきっかけは、毎日新聞で稲について「実りたわわ」という見出しを見たことです。普通は柿とかリンゴとか枝になるものではないかと思ったのですが、毎日新聞記事データベースを見ると、地域面を中心に稲についてけっこう使われています。
新語俗用も多く取り入れている三省堂国語辞典8版で「たわわ」を引くと
①たわむほどであるようす。「枝も―に実る」②〔俗〕大きく育ったようす。「―に実ったスイカ」
とあり、この「スイカ」の例もまさかと思ったら毎日新聞の見出しに使われていました。
中島みゆきさんには「た・わ・わ」という歌があり、女性の体の形容として使われています(「た・わ・わ」の後は「おまえを殺したい」「あいつをとらないで」と恨み言になるのがいかにもみゆき節なのですが……)。どうも対象はどんどん広がっているようです。
元々は「枝もたわわに」何かがなるという使い方で、「枝」がつくのが慣例でした。だから「実もたわわに柿がなる」は毎日新聞用語集でも誤用扱いにされ「枝も」と直すように指導しているのです。が、「枝も」を付けない例が広がるのと軌を一にするように、対象が枝になるものから豊かな実りそのものへと拡大しているように感じます。
「たわわ」は普通平仮名で書きますが、漢字では「撓」。これは「撓(しな)う」という訓読みと「不撓(ふとう)不屈」で使われる音読みトウで知られます。弾力があってしなやかに曲がるさまを表します。

その漢字の意味だけを取れば「枝」がないもの、例えば稲穂などに「たわわ」を使ってもおかしくないという解釈もできそうではあります。でもさすがに地面の上にゴロンとなっているスイカや、土の中にできる落花生にまで及ぼすのは拡大しすぎと言われかねないのではないでしょうか。
古今集、万葉集は「枝」付き
NHK放送文化研究所のウェブサイト=書籍「NHKが悩む日本語」(幻冬舎)所収=ではこんな問答があります。
Q 落花生の収穫の様子を番組で伝えるのに、「たわわに実った落花生」という表現は使えますか?
A 放送では、使わないほうがいいでしょう。「たわわに実る」は、伝統的には「枝がたわむほど多くの実をつける」という意味です。原則として、土の中の収穫物には使いません。
そこでは、枝はありませんが「イネ」も問題視されず「使われているようです」とあります。
これに対し、読売テレビの道浦俊彦さんは違和感を示しています(ウェブサイト「新・ことば事情」)。
「稲穂がたわわに実る」も、言ってしまいそうだけど、なにか違和感が。「稲穂」は「米粒の集合体」ですね。小さい。たとえ「集合体で大きくなっている物」でも、あまり小さなものは「たわわ」とは言わないのではないか。「一つで、ある程度の大きさがあるもの」に使う気がします。
なるほど確かにそんな語感があります。ただし「たわわ」の古い例を探っていくと、必ずしもそうとはいえません。
例えば古今和歌集の223は
をりて見ばおちぞしぬべき秋萩の枝もたわわにおけるしら露
白露というはかなげな水もハギの枝にかかると枝もたわんでしまうということでしょうから、ある程度大きな一つの物ではありません。
さらに「たわわ」のルーツを探っていくと、万葉集(2315)にまで行き着きます。
あしひきの山道(やまじ)も知らず白橿(しらかし)の枝もとををに雪の降れれば
この「とををに」は「たわたわ」とする本もあるそうで、これが「たわわ」になったとされています。つまり、この場合たわわにさせるのは「雪」です。
地中の物に使うのは行き過ぎ
時代は下り、徒然草の「たわわ」では「大きなる柑子(かうじ)の木の、枝もたわわになりたるが」と出てきます。このあたりから「枝もたわわに」というつながりが「大きな」果物という連想を働かせる表現になったのかもしれません。

ちなみに「枝も」の「も」は何を受けたものでしょう。並列の「も」なら何か前提がありそうですが、そのへんは日本語の曖昧さです。明鏡国語辞典3版の「も」の以下の用法に該当すると思われます。
さりげなくとりたてて、文意をやわらげる。「おなかもすいたし、食事にするか」「天気もいいから、散歩でもしよう」「一晩休めば、疲れもとれる」
つまり例えば「おなかもすいたし」は「おなかがすいたから」というほど切実な理由ではないようです。同様に「枝も」の「も」にほとんど意味はないといえるでしょう。そして時代が下り現代になると、枝そのものの重要性も減じて「たわわに」自体が豊かな実りの形容となり「枝も」がなくても違和感がなくなった――という流れなのかもしれません。
それで「枝も」がなくなるのだとしたら、枝を持たない植物について「たわわ」が豊かな作物の表現となるのも必然という気もします。

とはいうものの、植物すべて豊かな実りがあれば「たわわ」と使ってよいと判断するのは行き過ぎではないでしょうか。落花生やサツマイモなど地中になるものについて使うのは、今のところ避けたほうがよさそうです。
(2025年11月24日)
「たわわ」は岩波国語辞典によると「枝などが重みを受けてたわむさま」。この言葉は伝統的には「枝もたわわに」何かが実るという形で用いられ、枝がしなうほど実るさまを表しました。だから「柿」はふさわしいといえます。
しかし実際には枝はないのに「稲穂」も使われています。大辞林には「木の枝や稲の穂などに実がなったりしてしなやかに弧を描いて曲がっているさま」とあります。枝がなくても使えるという判断です。毎日新聞でもかなり使用例が見られます。
毎日新聞用語集では「実もたわわに柿がなる」は誤用と規定し「枝もたわわに柿がなる」に直すよう促しています。しかし実際の使い方では「枝も」を付ける例は少なくなり、それとともに枝になるもの以外の使用も増えているのかもしれません。落花生は地中になるものですからさすがに変でしょうか。それとも枝や地上に関係なくすべて豊かな実りへとイメージが拡大しているのでしょうか。
(2025年11月10日)