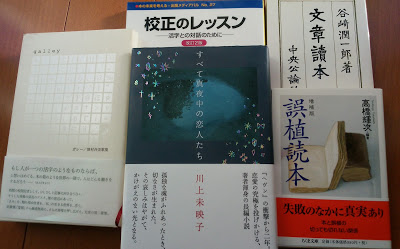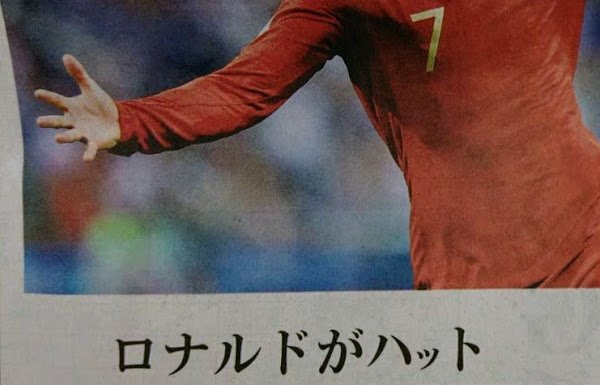台湾有事に関する高市早苗首相の発言が物議を醸しています。その内容はともかく、高市首相が「戦艦」という言葉を使ったのが気になってしようがありません。だって今、現役の「戦艦」はないはずですから。

目次
「存立危機事態」より気になる「戦艦」
いま日中間の国際問題となっている高市早苗首相の答弁。11月7日の衆院予算委で、立憲民主党の岡田克也氏の質問に対して飛び出しました。翌日の毎日新聞1面から引用します。
中国による台湾の海上封鎖が発生した場合の事態認定について問われ、集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」に認定される具体例に言及した。台湾有事と考えられるケースとして、海上交通路(シーレーン)の封鎖などを例示。その上で「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と答えた。
「戦艦」といえば、戦艦ポチョムキン、宇宙戦艦ヤマト……などと映画、アニメなどでなじんできたのですが、リアルな軍事にはとんと疎い私。それでも、いま戦艦というものは現役では存在しないらしいということは、どこかで読むか聞くかしていました。
高市さん、国会で「戦艦」なんて言葉を使って大丈夫なんだろうか、と気になりましたが、その後の内外の反応は主に、これまで曖昧にしてきた存立危機事態、つまり自衛隊を戦場に派遣できるケースとして台湾有事を明言したことについての是非であり、「戦艦」という言葉についてはあまり問題にされていないようです。私の認識が間違っているのでしょうか。
「世界で現役の戦艦は存在しない」
そこで「ミリタリー用語辞典」(野神明人著、新紀元社、2019年)で調べました。ちなみに同書は最初のページにも「軍艦をまとめて『戦艦』と呼んだり、軍用車両をまとめて『戦車』と呼んだりすることは、残念ながら一部の報道でも見られます」とあり、のっけから苦言を呈しています。
戦艦【せんかん】Battleship
強大な砲を搭載し主用攻撃兵器とする一方で、堅固な防衛力も備えた、海軍の主力大型戦闘艦。19世紀末に登場した戦艦の主砲は30~34㎝の口径であり、その後、第二次世界大戦最大の戦艦である日本の「大和」型戦艦に搭載された46㎝砲まで拡大した。一方、戦艦の防衛力は、「主要部分の装甲が自艦の主砲の直撃にも耐える」ことを定義とされてきた。そこで主砲は強力でも、装甲がそこまでに至らない艦は、巡洋戦艦として区別された。第二次世界大戦までは、戦艦が海軍の主力艦であった。しかし緒戦で日本軍が行った真珠湾攻撃やマレー沖海戦で、航空機により戦艦が撃破されることが明らかになり、その後、主力艦の地位は空母にとって代わられる。沖縄戦で日本が誇る「大和」が、空母艦載機の波状攻撃で沈められたのが、その象徴となった。一方、アメリカ海軍が第二次世界大戦末期に就役させた「アイオワ」級は、戦後も長らく使われたが、1992年に退役した3番艦「ミズーリ」が最後の戦艦となった。現在は世界で現役の戦艦は存在しない。
最初の「主用攻撃兵器」の「主用」は「主要」の誤りでしょうか。その他、「戦車兵」の見出しにも明らかな脱字があり、この本の校正大丈夫?と思いました。念のためほかの本を見ると2025年刊行の「図説 海戦の戦術全史――作戦・兵器・艦船の3000年」(原書房)にも、1991年の湾岸戦争におけるアイオワ級戦艦が最後の活躍だったとあります。そして――
2006年に最終的にアメリカ海軍のリストから抹消された。除籍された理由の一端は、これらの艦船が、高度な技能を有する乗組員を大勢必要とする点にあった。戦艦1隻につき、巡洋艦4隻分の人員が必要となるのである。
中国軍のことは書かれていませんが、戦艦を有しているという情報は「中国軍、その本当の実力は――中国軍は台湾を着上陸侵攻できるのか」(樋口譲次著、国書刊行会、2023年)にもネット上でも見いだせません。戦艦は今、ハワイに「ミズーリ」、横須賀に「三笠」などが記念艦として展示されているくらいで、歴史的遺物のようです。

高市さん、ご存じなかったか
だから正確には「軍艦」と言うべきところでしょう。それなのに高市首相はなぜ「戦艦」という言葉を使ったのでしょうか。
高市さんは防衛相を経験していないので、その方面の正確な用語を知らなかったのかもしれません。また、単なる言い間違いという可能性もなくはありません。
ただし、広辞苑で「戦艦」を引くと
①戦争に用いる船。軍艦。戦闘艦。②軍艦の一種。最も卓越した攻撃力と防御力を有する大型艦で、第二次大戦までは水上兵力の中心。
となっています。高市首相はこの①の意味で「戦艦」と言っているのであり、一般語としては問題ない、という見解もありえます。
しかし、この日首相は午前3時に出勤して想定問答に入念に目を通していたはず。その原案は各省庁、この場合は防衛省が作成すると思われます。専門家が「戦艦」という用語を持ち出すだろうかという疑問は拭えません。
国際政治学者の舛添要一氏もX(ツイッター)で
防衛省がきちんとレクをしていれば、あのような不用意な発言はなかったかもしれない。「戦艦」などという言葉は今は使わない。
と述べています。つまり、あの発言は高市首相自身から出たと見るのが自然でしょう。
著書で有事「戦艦」「艦艇」使い分け?
実は高市さんが「戦艦」という言葉を使ったのは今回が初めてではありません。昨年9月の自民党総裁選に際してのテレビ討論で、中国による台湾の海上封鎖が発生した場合について問われ、
存立危機事態になるかもしれない。とにかく日本の生存に関わる。シーレーン(海上交通路)も使えなくなり、場合によっては東京と熱海の間くらいに中国の戦艦だとか、軍用機が展開するような事態になる。
と述べています。また同月発行の著書「日本を守る 強く豊かに」(WAC)でもこう書いています。
台湾と与那国島は約百十キロメートルしか離れていません。「台湾有事=東京都と熱海市の中間地点に中国の戦艦と戦闘機が展開する」と想像していただければ、(中略)日本は確実に戦域に入ります。(第7章「中国の理不尽なやり方に屈してはならない」より)
こうしてみると、高市さんは単に正確な意味を知らないというより、何か意図的に「戦」という言葉を使っているのではないかという気もしてきます。
というのも、先の高市さんの著書の別の部分では
日本周辺海空域全体で見ると、特に中国軍の艦艇・航空機によるものが活発化しています。中国の海軍艦艇による日本領海内航行が確認されました。(同)
と、ここでは「戦艦」という言葉を使っていないのです。
例えば、台湾有事の文脈ではあえて刺激的な用語で国民に危機感を植え付けたいとか、そういう意図があって「戦」の字を使っているという可能性も考えられます。
しかし、一政治家として発信するならともかく、一国の首相つまり自衛隊の最高指揮官の国会発言としては用語の厳密さを欠き、軽率だったのではないでしょうか。
トランプさんは「戦艦を復活させたい」
ところで、本当に戦艦は過去の遺物となったのでしょうか。
10月のブルームバーグの報道によると、トランプ米大統領は「戦艦を復活させたい」と言い出しているそうです。
「中には『いや、あれは古い技術だ』と言う人もいる。しかし、私はそうは思わない。あの大砲を見れば、古い技術だとは言えないだろう」「砲弾はミサイルよりも費用がかからない」とトランプ大統領は語った。
と、発言を引用した上でブルームバーグは
現代の海軍では、かつてのように大砲を持つ戦艦が活躍する場はなくなったのだ。
将来、例えば中国との戦争では、海の上や水中から攻撃してくる新しい敵に向き合う状況となり、ミサイルの攻撃を受けることになるとアメリカの軍関係者や作戦担当者は予想している。彼らによると、ミサイルやドローンに対するさまざまな対抗手段を備えることが生存性を高める上で重要であるという。少なくとも当初の設計のままでは、戦艦はそうした戦闘にはあまり適していない。
と指摘しています。つまり派手好きのトランプさんの妄言ということがうかがわれます。しかしこれまで横車を押すようなことを実行してきた彼のこと、戦艦を復活してその名を「トランプ」にしようともくろんでいる可能性もあるかもしれません。

そういえば、日本政府では自衛隊の階級を「1佐」「2佐」から「大佐」「中佐」などに変更することを検討しています。なんだか日米とも戦争への復古というか郷愁が感じられる動きのようではないでしょうか。
本題に戻って、個人的な提案です。こじれた日中関係を修復するには、元の高市さんの発言を撤回するしかないと思うのですが、日本政府としても高市さん個人としてもやりたくないでしょうから、「戦艦」という用語が不適切だったという理由で発言内容を削除するというのはいかがでしょう。中国向けには事実上の撤回というメッセージを送り、国内向けとしては用語関係についての修正にとどめ中国の圧力に屈したわけではないと言い訳でき、誤解の多い「戦艦」という言葉の意味内容も周知できる。これぞ政治家が得意な曖昧戦略だと思いませんか、高市さん。……応じるわけないですね。
【岩佐義樹】