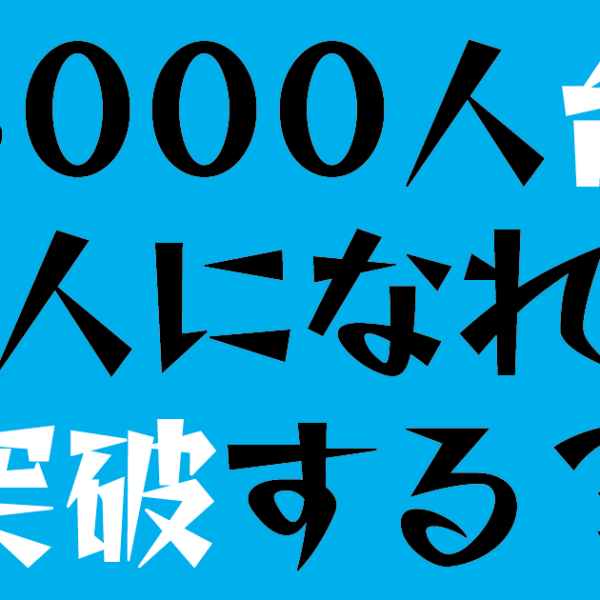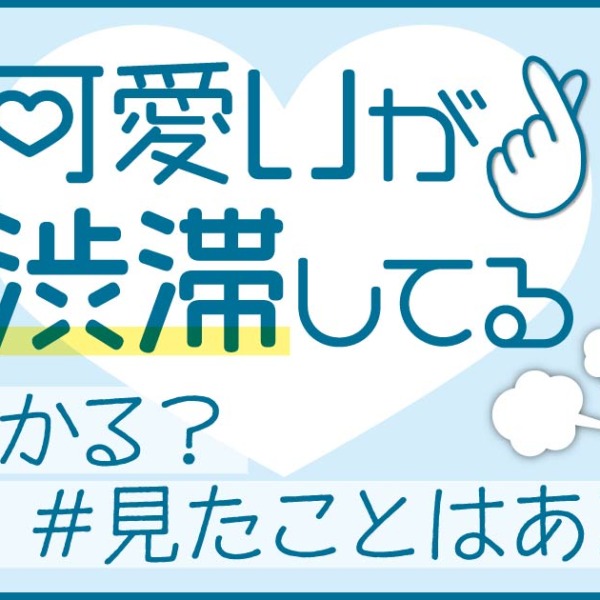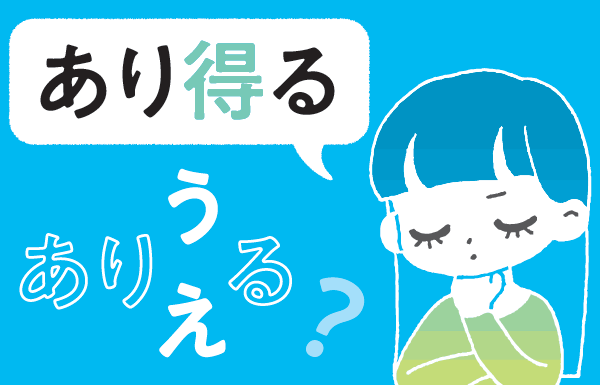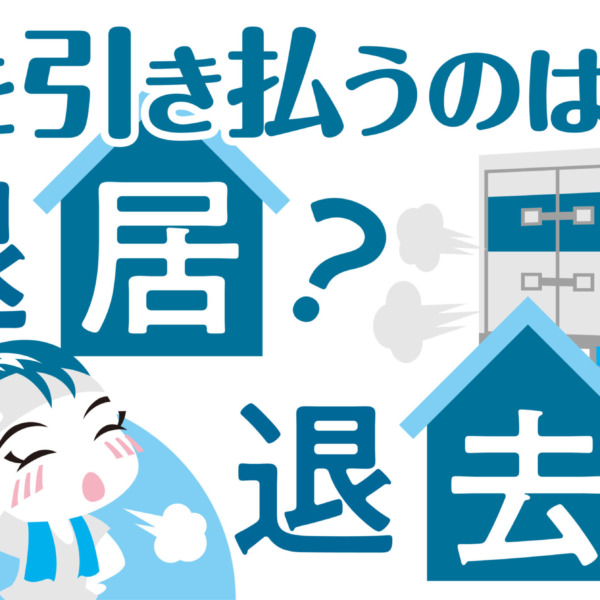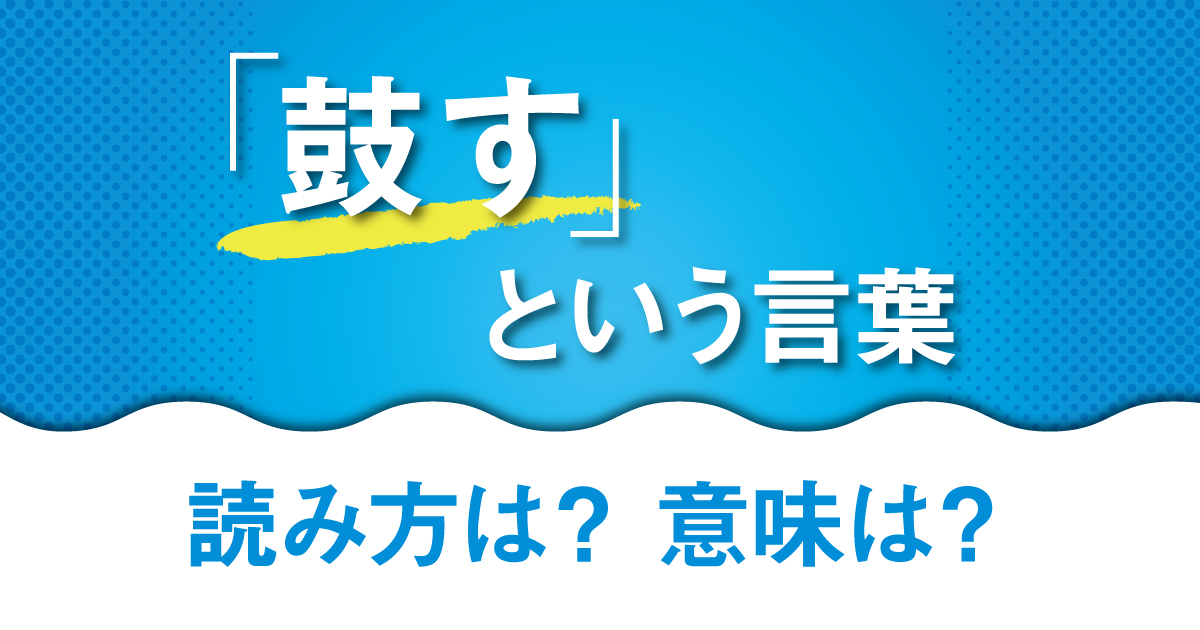
「鼓す」という言葉について伺いました。
目次
4分の3は読み方・意味ともよく分からず
| 「鼓す」という言葉、読み方・意味は分かりますか? |
| 読み方・意味とも分かる 9.1% |
| 読み方は分かるが、意味はよく分からない 3.1% |
| 意味は分かるが、読み方はよく分からない 13.7% |
| 読み方・意味ともよく分からない 74% |
「鼓す」という言葉については「読み方・意味ともよく分からない」とした人が最多で、ほぼ4分の3を占めました。全国戦没者追悼式の石破茂首相の式辞では「寛容を鼓し」という形で使われましたが、使用例としては相当珍しいもので、その場にいた人たちも耳で聞いただけでは理解できなかったかもしれません。
鼓する? 鼓す?
「鼓す」は「こす」と読み、多くの国語辞典には「鼓する」という形で記載されています。辞書の項目としては、
こ・する【鼓する】[他サ変]①楽器などを打ち鳴らす。「洞裏に瑟(しつ)を―が如く〈漱石〉」②勇気などを奮いたたす。「勇を―」[文]こ・す
(明鏡国語辞典3版)
のようなものが一般的でしょう。②は「鼓舞する」とほぼ同義です。「鼓す」という形は文語形として挙げられていますが、同じ明鏡の「勇」の項目に出てくる例は「勇を鼓す」。「勇」の項目で「勇を鼓する」と書いている辞書は、筆者の見た範囲では中学生向けの三省堂の例解新国語辞典(10版)のみで、他は軒並み「勇を鼓す」でした。
実際のところ、終止形としての「鼓する」を目にすることもほとんどありません。明鏡の漱石の用例(「吾輩は猫である」のもの)は「鼓するが如く」ですが、これは文語サ変動詞の連体形です。そのあたりを考慮してか、「鼓す」を文語としてではなく「サ変動詞『鼓する』の五段化」として、「鼓する」とは別に項目を立てる大辞林(4版)のような辞書もあります。

しかし更に言うと、データベースなどで見られる現代の用例は連用形の「勇を鼓し、」「勇気を鼓して」のようなものばかりで、「鼓す」にしろ「鼓する」にしろ見かけることはほぼありません。連用形では口語のサ変でも文語のサ変でも五段でも形は変わらず、終止形がどうかというのはあまり意味がないかもしれません。動詞は終止形で載せなければならないという、辞書の難しさも感じます。
その他の用法は…
「勇を鼓す」以外の用例を青空文庫で探すと、「舌を鼓す」が見られます。「舌を鼓し、腹打つ事のありがたさよ」(岸田国士「生活のうるほひ」)は、文字通り舌鼓を打つこと。「吃る鈍舌を鼓し」(大町桂月「夜の高尾山」)は、舌を励まして、とも読めますが、漢語の「鼓舌」は「したをふるってしゃべる」(新選漢和辞典)の意で、舌をよく動かして、の意かもしれません。
石破首相も使ったのだし国会会議録はどうか、と検索してみると、用例はやはりほぼ全てが「勇を鼓し」「勇気を鼓し」「勇氣を鼓し」です。ただ一つ「琴柱(ことじ)ににかわして琴を鼓す」との言い回しが1961年の農林水産委員会で使われていました。辞書には「柱(ちゅう)に膠(にかわ)して瑟(しつ)を鼓す」との形で出ています(大辞泉2版)。いわく「琴柱を膠で動かないようにして瑟を弾く。状況の変化に対応できないことのたとえ」だそうです。

いずれにしても古めかしい言い方であることは間違いありません。高校生向けとされる三省堂現代新国語辞典(7版)は、「鼓する」の項目で「勇を―」の用例の後に「古い言い方」と注記しています。最も使われる「勇を鼓す」でもそのように扱われるなら、「鼓す」自体がよく分からない語になるのも無理のないことかもしれません。
聞く人の耳は素通りしたかも
石破首相は8月15日の全国戦没者追悼式の式辞(全文)で「未(いま)だ争いが絶えない世界にあって、分断を排して寛容を鼓し、今を生きる世代とこれからの世代のために、より良い未来を切り拓(ひら)きます」と述べました。「寛容を鼓し」が珍しい言い方であることは、ここまで書いたことから分かるのではないかと思います。通常なら「寛容を重んじ」などとなるところでしょうか。
とはいえ石破首相は、それでは物足りないと思ったのでしょう。単に大切にするだけではなく、もっと勢いや力強さを与えるような表現にしたかったのでは。結果的に耳慣れない言葉を使うことになり、メッセージの内容以前に言葉の選択の問題として、聞く人の耳は素通りしてしまったかもしれないのですが……。首相の事情をそんたくするなら、あえて「奮いたたせる」意の言葉を使ったというのは、党内で突き上げを受け続けた自分自身を励ます気持ちも反映していたのでしょうか。
(2025年09月08日)
「鼓す」は「こす」と読みます。国語辞典では「鼓する」という口語の形で見出し語に取られることが多いですが、主な用例である「勇を鼓す」ではもっぱら「鼓す」が使われます。意味は「楽器などを打ち鳴らす。また、かき鳴らす」「気力を奮いたたす」(大辞泉)。「勇を鼓す」なら「勇気を奮い起こす」(同)ということです。
石破茂首相が、8月15日の全国戦没者追悼式の式辞で「分断を排して寛容を鼓し……」と述べていました。内容をおいて気になったのは、官邸の発表文でも官邸ウェブサイトのテキストでも「鼓(こ)し」と読み仮名が入っていたことです。
テキストでは常用漢字に含まれる文字であっても「御前(おんまえ)」「尊(とうと)い」といった読み方の複数ある言葉には読み仮名が付いていますが、「鼓し」には「こし」以外になじむ読み方はなさそうです。もしかすると、あまり一般的な用法ではなく読みにくいと考えたのかもしれません。それなら違う言葉を使う方がよいのでは……とも思いましたが、まずは皆さんの意見を聞いてみる方がよいでしょう。「鼓す」という言葉、いかがでしょうか。
(2025年08月25日)