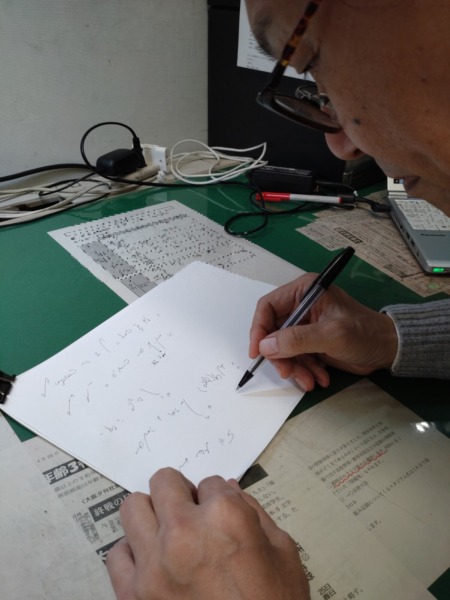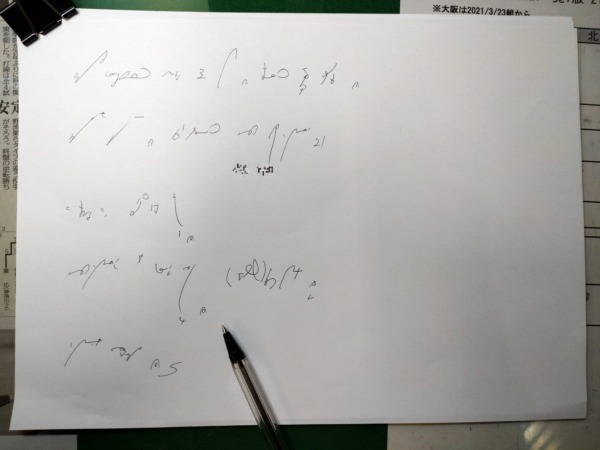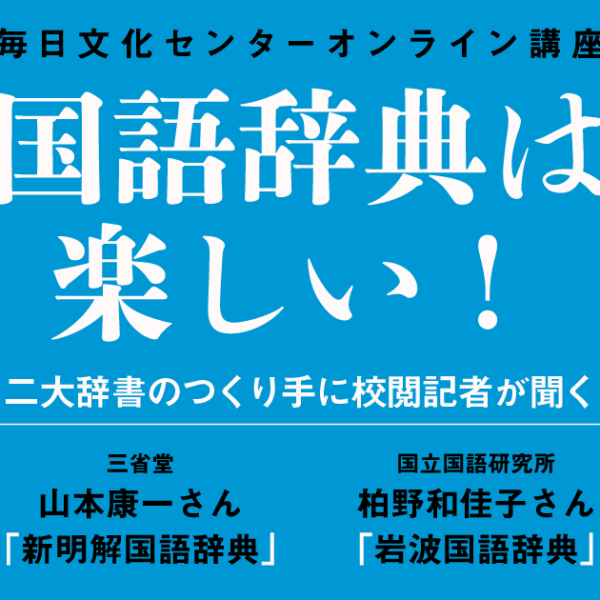パソコンもファクスも無かった時代、原稿はどう送信していたかご存じですか。そんな時代に活躍した「速記者」出身の校閲記者は社歴40年超。最古参として今も誇りを持って業務に取り組む記者が見てきた変化と、今も変わらぬ紙面作りの要諦を語ります。
目次
原稿は「速記者」が文字起こし
「パチパチパチ、カチカチカチ」。パソコンをたたく記者、編集者。今やパソコンの中で記事が書かれ、パソコンの中で編集作業が進む。新聞製作もガラッと様変わりした。
私が「毎日新聞最後の速記者」として入社した1980年ごろは、今のようにスマートフォンがあるわけでもなく、簡易のファクスすら設置されていない支局もあった。携帯とはいえども肩から掛ける大型のものしかなく、数も限られていた。原稿の送受稿は支局から電話で速記者に吹き込み、速記者が文字に起こすというのが主流だった。
速記者は大阪本社の場合、十数人が在籍し、いつ鳴るともしれぬ電話のベルに耳を澄ます。時間がある原稿は速記で取り、誰もが読める文字に書き直す。
締め切り間際になると緊迫。速記は使わず、雑用紙(新聞紙を廃物利用したはがき大のわら半紙の束)に、1行分を1枚に書く。隣では地方部デスクが2~3枚書くごとにひったくり、サブデスクが走り書きした原稿の〝破片〟を持って活版場へダッシュ。アナログ全開のスリリングな場面が展開される。これが新聞社なのだ。
送受稿は人と人とのやり取り。取材先と支局、支局と本社。本社内でもいろいろな人の手が入り、活字の原稿ができあがる。
人が介在するとどうしても間違いが生まれる。集中のうえにも集中して原稿を仕上げるが、時としてデスクから雷が。「お~い、ここ意味が分からん」「住所が間違ってるぞ!」などなど。おびえながら仕事をしていたのが昨日のことのように思い出される。
1音の聞き違いで大惨事
「最近はOA機器も普及し、誤字や誤解は少なくなったと思います。電話だけで原稿を送っていた時には、どんな言い方で伝えていたのでしょうか」。以前、読者の方からこんな質問をいただいたことがある。
確かに、1音違いで意味が変わってしまうものから、価値が変わってしまうもの、また、固有名詞に至るまで、さまざまな〝聞き間違い〟が存在する。
「開始」と「廃止」。1音違うだけで180度意味が変わってしまう。こういう場合は「始める開始」「やめる廃止」などと言葉の意味を添えてみる。「金」と「銀」。「銀」メダルでも喜ぶ選手がいれば悲しむ選手もいる。一概に価値判断できない。「ゴールドの金」「シルバーの銀」など英語を組み合わせてみよう。「協議会」と「評議会」。全く別の組織を批判してしまうかも。「十」に「力」三つの「協」、「言」べんに「平」の「評」などと漢字を分解して説明すると分かりやすい。また、誰もが知っている動物や植物などの名前で説明するのも一考です。試してみては……
などと返答したのを思い出した。
「完全原稿」という幻想
校閲で30年、編集者として10年過ごした。この間、機械化も進み前述のようにパソコンの中での新聞製作だ。「記者本人が入力するので、間違いのない〝完全原稿〟。校閲の仕事も楽になるはず」などという、あり得ない説明を受けたものだった。ふたを開ければ変換ミスやら事実関係のミスなど想像通りの間違いは後を絶たなかった。
今、校閲記者は2、3台のパソコンを駆使してネット検索に打ち込む。息抜きの〝バカ話〟に花を咲かせる余裕すらない。
とはいえ、劣悪な職場環境とばかりはいえない。リモートワークが増え、いろんな立場でも勤務が可能だ。校閲も編集も東京と大阪で仕事のシェアをする。アナログで古くさかったあの〝新聞社〟がである。入社時には考えられなかったな……。仕事の仕方、求められるもの、時代とともに変わっても、校閲の仕事に誇りを持ち、きょうもパチパチ、パソコンをたたく。
土壇場でこそ落ち着いて
少し横道にそれた、閑話休題。
今も締め切り間近になると、電話での問い合わせも増える。バタバタし頭に血が上り冷静な判断ができなくなることもしばしば。こんな時こそ落ち着いて、相手に誤解を与えないようにきっちり伝えたい。自戒の念も込めて。中途半端に自分で判断しないことが肝心で、少しでも疑問があればくどいほど聞き返すのもアリだ。
入社当時、ある先輩からこんな〝掛け合い漫才〟のような話を聞いた。
「ある皇族が寺で亀をご覧になった」という原稿での出先の記者と支局デスクとのやり取り……。
デスク 「ご覧になったのは大きな亀だな」
記者 「そうです。大きな鐘です」
デスク 「念のためだが鶴亀の亀だな」
記者 「そうです。釣り鐘の鐘です」
デスク 「もう一度聞くが動物の亀だな」
記者 「そうです。大仏の鐘です」
双方の思い込みからのすれ違い。やっぱり100%の完全原稿は望めないのか。「亀」だけにゆっくり焦らず「鐘」だけに核心を突けば相手に響くはず。きょうも頑張っていきましょう!
【坂本一夫】