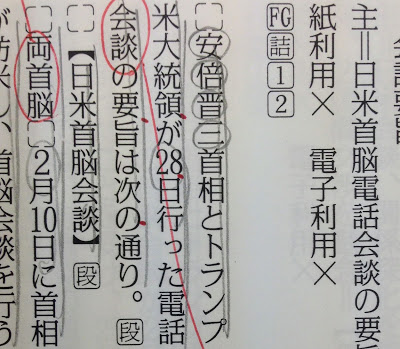「討ち入りと旧暦」に続き、忠臣蔵にちなんだ話題として「肝煎り」という言葉について考察します。
といっても、忠臣蔵と肝煎りとどういう関係があるのか、歴史に詳しくないと分からないかもしれません。江戸城松の廊下で浅野内匠頭が刃傷に及んだ相手である吉良上野介の幕府内での役職が「高家肝煎(こうけきもいり)」だったのです。
「高家」というのは、広辞苑によると「幕府の儀式・典礼、朝廷への使節、伊勢神宮・日光東照宮への代参、勅使の接待、朝廷との間の諸礼をつかさどった家。室町時代以来の名家、大沢・武田・畠山・大友・吉良など二六家が世襲」とあります。「吉良」が出ることにご注目ください。
では「肝煎」は? やはり江戸幕府の職制としては「高家の上席」(広辞苑)、「同職の中で、頭だって職務を取り扱う者」(日本国語大辞典)だそうです。吉良上野介は「高家筆頭」とも書かれるように、高家の中でも別格の存在だったようです。
さて、江戸時代の役職という意味は別として、現代でも「肝煎り」という言葉はよく使いますよね。「首相肝煎りの会議」とか。この「肝煎り」の使い方は、辞書の語釈と微妙に違うという指摘がありました。
一般的な辞書では「中に立って世話をすること。また、その人」(明鏡国語辞典)、「仲間の人間関係をまとめるために骨を折ること(人)。取りもち。世話(人)」(新明解国語辞典)となっています。
「首相肝煎りの会議」というのは、首相が間に入って世話を焼くというイメージではなく、たぶん首相がトップダウンで設置を命令し、議論も主導する会議なのでしょう。だとすると確かに、普通の辞書の語釈と違ってきてしまいます。
しかし、歴史上では「上席」つまり「頭に立ってどうこうする役割」という使い方があったことも事実です。ですから、誤用とまではいえないでしょう。むしろ、「中に立って世話をする」の意味が拡大し、上に立つ者の主導的な役割という歴史的な意味が復活しているのではないでしょうか。
また、「暮らしのことば 語源辞典」(講談社)によれば、肝煎りとは「本来は、肝を煎るように心をいらだたせ、やきもきする意」ということです。最近の「首相肝煎り」という言葉には、「中に立って世話をする」という長屋の隠居のような悠長なイメージよりむしろ、できるだけ早くトップダウンで物事を決めなければという首相の「いらだち」のようなものさえ感じられます。こういう意味でも、言葉の先祖返りといえるかもしれません。
なお、「肝入り」という表記は歴史的にも少なからずされていたようで、認める辞書もあるのですが、語源から考えると不適切でしょう。2010年の常用漢字改定で「煎」の字が入ったこともあり、「肝煎り」と書きたいものです。「角川必携国語辞典」ではわざわざ「『肝入り』は誤り」と注記しています。この注の筆者はたぶん「肝入り」という字を見るたびに「心をいらだたせ、やきもき」していたに違いありません。
【岩佐義樹】