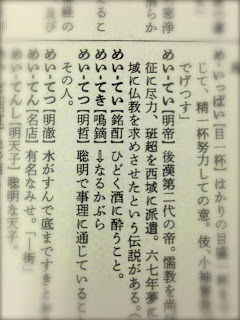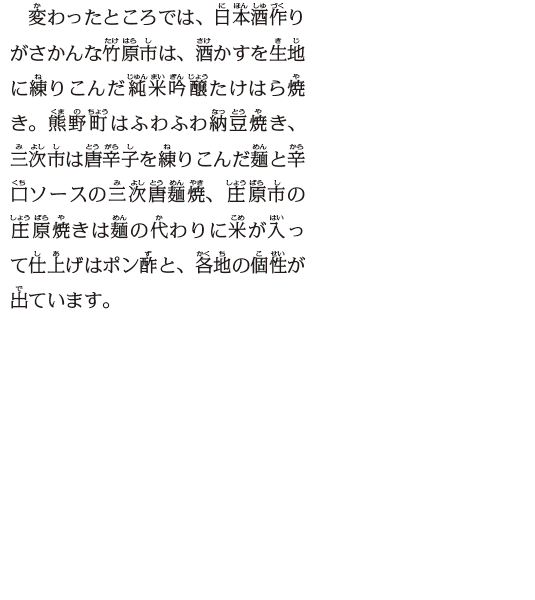サッカーのブラジル・ワールドカップ(W杯)も大詰めです。日本代表の1次リーグ敗退で国内的には若干、熱狂が引いた感もしますが、21年前のJリーグ発足以前の無関心・無理解の日本サッカーを取り巻く雰囲気とは雲泥の差だと思います。まして1968年メキシコ五輪銅メダル獲得の後に、「学校のサッカー部」「企業のチーム」ではない「クラブチーム」、草野球ならぬ「泥蹴球クラブ」を私が結成したころのサッカー事情に比べれば、同じ日本とは思えません。
当時、私たちの泥蹴球チームは、30分ハーフの試合に1対8で負けたことがあります。7分半に1点入れられた計算ですが、勝った方は蹴れば得点、こちらはキックオフからハーフタイムを挟んでタイムアップまで敵が攻め続けてくるように感じていました。トラの子の1点も誰が蹴ったのか、分からないまま終わりました。こんな大敗北でも、「取った!」という忘れられない1点があれば、いい試合だったと私は何十年たっても思っています。
さて「校閲記者」という私たちの仕事を「縁の下の力持ちですね」などと褒めてくださる方もいます。誤りを見つけて紙面にならないように防ぐという意味で、サッカーの「ゴールキーパー」のように見られることも多いです。キーパーは、自陣ゴールを遠く離れて攻撃に加わり得点を狙う、という緊急事態もありますが、通常は味方ゴールをただ一人、守らなければいけません。その他の選手は前後に入れ替わって攻撃に加わったり、守備の補強をしたりということを頻繁に行いますし、そのように全体的に動くことが今のサッカーでは必須不可欠の要素なのでしょうが、キーパーはやはり特殊任務を帯びているのです。
もちろん失点が全くゼロであれば負けることはありませんが、これは盤石の守備が行われたうえでのことですから、かなりハードルが高いといえます。失点を防ぐことだけを目指し、守ることばかりに目が向いて、消極的に引きすぎてしまえば、すきを与えてしまいます。逆に、果敢なタックルのような先制攻撃的「一発必殺」な守りも、限度を越えると反則をとられ、フリーキック、場所によってはペナルティーキックを敵に与えてしまいます。守備陣は我慢して我慢して、攻撃の端緒へとつなぐという任務を果たした末に「評価」されるのです。校閲の仕事でも、時々、出稿元や編集者とのやりとりの末に「言っていることは納得いかないけれど、相手が正しいっていうなら、そういうことにしておこう」とおさめてしまいたくなる場面がありますが、そういう妥協は決して「守りの校閲の姿勢」とはいえません。目の前に迫ってくる「間違い=敵」を撃退するという「戦闘」に打って出るスピリットをずっと持ち続ける体力勝負に勝たなくてはなりません。それが「縁の下の力持ち」との期待に応えることだと思います。
【岸田真人】