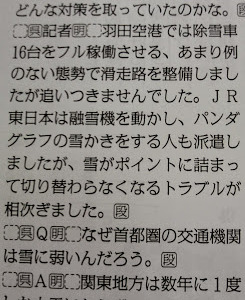「『天国でヒワマリ咲かせて』――朝刊社会面で、お恥ずかしい間違いを出す羽目に……」。数年前、大阪本社校閲グループ備え付けの「連絡ノート」に私が記した一節です。
ある事件で亡くなった児童の一周忌に、同級生たちがヒマワリの種を結んだ風船を空に飛ばして追悼したという記事に冒頭の見出しが付いたのですが、文字が引っ繰り返っていることに、担当の私をはじめ編集局の誰も気付かず紙面化したのです。
見出しは最も目立つため、誤りが発生すると多くの読者から指摘がくるのが通常。ましてや平易なカタカナとあっては、「そんなことも分からないのか」とお叱りの声が相次いでもおかしくないところ。
しかし、その時寄せられた指摘は1件。自分のミスを棚に上げるわけではありませんが、これはカタカナの誤植が意外と見付けにくいことを示す一端ではと考えるのです。この件以降もエベレストがエレベスト、オンブズマンがオンズブマンなどとなっているのにだまされたことがあり、厄介だと言えます。
カタカナは視覚的に一塊として捉えてしまい、見た瞬間に正しく並んでいるものと錯覚するのが一因でしょう。これまでの経験から、見逃しやすいパターンを挙げると(正解は省きます)、上記の3例やアガリスクのような「入れ替わり」、サンフラシスコ(脱字)、ダイオキンシン(余分な字)、チェニジア(一字違い)、カッツポーズ、プルペン(濁音、半濁音)などがあり、落とし穴にはまりそうな形態はさまざまです。
原稿を点検する際、主に漢字の方に間違いが潜んでいないかにどうしても注意が向きがちですが、一見単純そうなカタカナを侮らないことも大切。若手記者には「一字ずつ傍点を打ちながら点検するくらいの慎重さが必要だよ」と助言しています。
ところが先日、私がチェックした記事で、「カタカナ」という言葉そのものが「カタカタ」でスルー。同僚が発見して事なきを得ましたが、文字通りその怖さを認識するとともに、慎重さを養う修業が足りなかったのは私の方だったと痛感しました。
【宇治敏行】