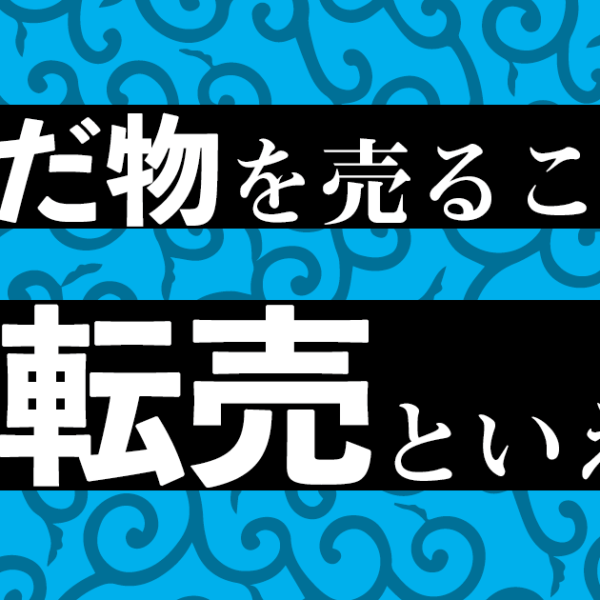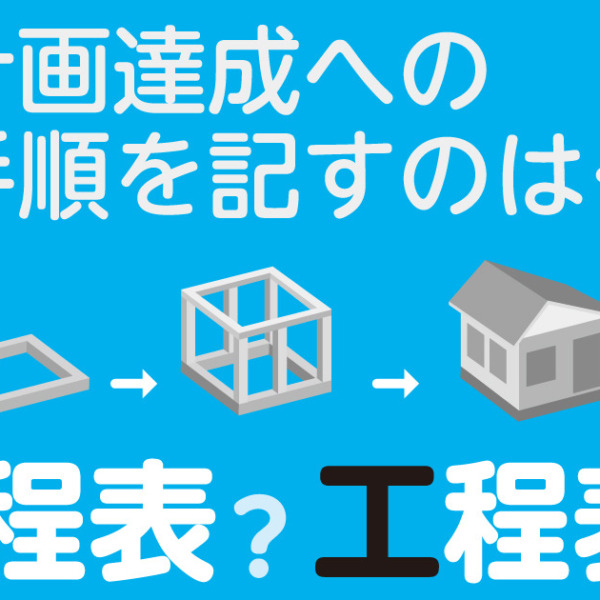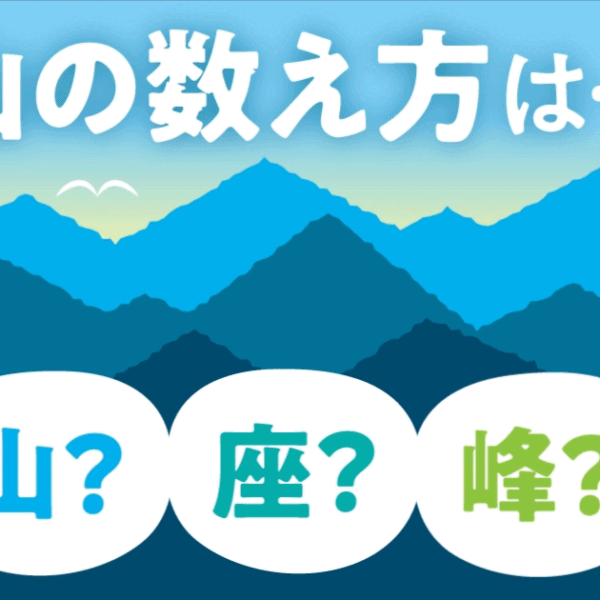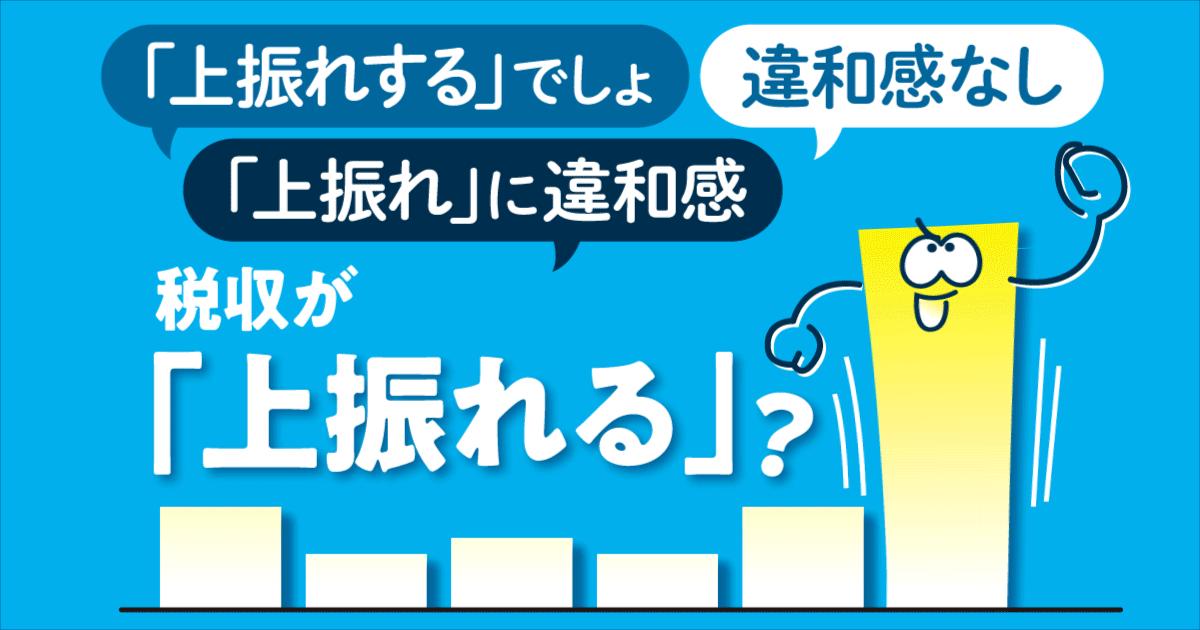
税収などが「上振れる」という書き方についてお聞きしました。
目次
8割近くが「上振れる」に抵抗
| 税収などが「上振れる」――違和感ありますか? |
| 「上振れ」自体に違和感がある 36.5% |
| 「上振れする」なら許容範囲 41.4% |
| 違和感はない 22.2% |
「上振れする」なら許容範囲とする回答が最多となりましたが、「上振れ」自体に違和感があるとした人も多く、合わせると「上振れる」に8割近くが抵抗を感じていることが分かりました。
経済白書にも「上振れる」
質問のきっかけは、予想を上回った税収の扱いが参院選での争点の一つになったことです。例えば国民民主党の玉木雄一郎代表は6月の党首討論で「上振れた税収は自民党のものでも公明党のものでもない。一生懸命働いている納税者のものだ」と述べました(国民民主党のニュースリリースより)。
玉木さんは1993年大蔵省入省の財務省出身ですから、こういう一般的でない言葉遣いが出るのでしょう。ちなみに現代日本語書き言葉均衡コーパス「少納言」での検索を手掛かりに調べると、1982年経済白書に税収に関してこういう文例がありました(年度は昭和)。
前者は当初見通しに比べ常に下振れしているわけではなく,51年度,55年度のように上振れる年度もみられたが,後者は一貫して下振れしていることがわかる。
国会ではもっと古くから言われているようですが、書き言葉でも経済白書に使われるくらいですから、経済関係省庁では少なく見積もっても半世紀の使用歴があるのでしょう。

「前倒す」も官庁俗語から
実は新聞の経済面でも「上振れる」は時々出ています。毎日新聞のデータベースで確認できる限りでは、2005年の日銀「展望リポート」の引用の形で現れ、その後、地の文でも散見されるようになります。「下振れる」はもっと前の1998年から見られます。
思うに、経済部記者も取材相手の用語に染まり、一般的な語と思ってしまうのかもしれません。本来なら校閲が「待った」をかけるべきだと思うのですが……。
似たような例としては「前倒し」があります。岩波国語辞典によると「『繰り上げ』でも済むのに、一九七三年ごろに官庁俗語として現れたのが、広まった語」。その名詞の動詞化として「前倒しする」とともに「前倒す」という奇妙な使い方や、「後ろ倒し」という新語も生じました。
ただ、新しい言葉が発生するにはそれなりの必然性があると考えてみましょう。官僚にしてみれば、計画は予定通りに執行させたいという気持ちが、予定通りにいかない場合「倒す」という言葉になって表れたのかもしれません。
「上回る」とどう違うか、AIに聞いてみると
「上振れ」はどうでしょう。「予想より上回る」でもよさそうなのに「上振れる」が使われるのはなぜでしょう。

試みに、Microsoft社の人工知能(AI)、Copilotに「上振れる 上回る 違いは」と聞くと、「上振れる」には「主にゲーム、投資、ギャンブルなど、運や確率が関わる場面で使われます。一時的・偶然的な良い結果というニュアンスが強いです」との答えでした。ゲーム、投資、ギャンブルでも使われるとは知りませんでしたが、察するに元は経済用語だったのが拡大し、そちら方面で使われる頻度が大きくなっているのでしょうか。
経緯はともかく「一時的・偶然的な良い結果」のニュアンスがあるという解析は、税収の予測という面からも的を射ているかもしれません。まさに「上振れる」を使っている、今年7月3日付毎日新聞経済面の「ゼロからわかる!」から断片的にですが引用しましょう。
税収が上振れるのは、正確な見通しを作るのが困難なためだ。
使う指標のルールはなく、指標の組み合わせには知識と技術が必要だ。「税収の分析は担当部署の伝統芸であり、職人技」(財務省関係者)という。だが、綿密に「当てに行っている」担当者でも、完璧に未来は予測できない。
そもそも、税収は上振れることもあれば下振れることもある「水もの」。安定的な財源として期待するのは難しいのが実態だ。
なんと、「職人技」で「当てに行っている」とはまるでギャンブラーではありませんか。当たるも八卦(はっけ)、当たらぬも八卦?
ギャンブル的かどうかはともかく、税収の見通しは「上回ることもあれば下回ることもある」より「上振れることもあれば下振れることもある」と書くほうが、常に上下に揺れ動く不安定さをイメージさせるとはいえそうです。
深読みすると、財務省としては「税収が上振れしたのはあくまでもたまたま。それを当てにしないほうがいいですよ」という遠回しのけん制が「上振れ」の用語に秘められているのかもしれません。まあ「そんなこと知ったことか」と言わんばかりに政治家は選挙で税収上振れを財源として当てにしていたのですが。
「上振れる」はブレた日本語では?
さて、三省堂国語辞典8版では「上振れる」「下振れる」を経済用語として認めていますが、新用法をすぐ採用するこの辞典の性格からいって、それを根拠に新聞で堂々と使っていいとはいえません。広辞苑、岩波国語辞典、新明解国語辞典は名詞の「上振れ」「下振れ」も含め載せていません。大辞林は4版で「上振れ」「下振れ」を採録したものの「上振れる」「下振れる」は示しませんでした。
面白いのは明鏡国語辞典3版で、「下振れ」は見出し語にしているのに「上振れ」は「下振れ」の対義語として付記するだけで見出し語にしていません。「下振れ」の方が頻度が大きいためでしょうか。いずれにせよ「下振れる」は採用されていないことからも、動詞の拡大には歯止めをかけていると受け止めることが可能でしょう。
たとえ経済の専門家が「上振れる」「下振れる」と言っていても、それは話し言葉のブレと受け止めるべきではないでしょうか。文字化する際は1字添えて「上振れする」「下振れする」と書くことをお薦めします。
(2025年08月04日)
「上振れる」や逆の意味の「下振れる」は主に経済関係の記事で使われます。例えば「税収が上振れる」というと見通しより増えることですが、説明されなくても意味はお分かりですよね。
でも、日本語としてはどうでしょう。広辞苑は「上振れ」も「下振れ」も載せていません。当然「上振れる」「下振れる」もなし。一方、新語採録に積極的な三省堂国語辞典は「上振れ」「下振れ」をそれぞれ見出し語に取り、名詞のほか「~する」という動詞にもなるとした後、「上振れる」「下振れる」も動詞形として付記しています。
経済界では日常的に使われている言葉かもしれません。しかし普通の家庭で「コメの値段が上振れている」なんて言わないでしょう。一般紙の場合、「上振れる」と書いてあるのを見ると、業界寄りの姿勢を感じてしまいます。「上振れする」なら許容範囲と考えられるかもしれません。いや、「上振れ」という名詞自体も業界用語で使うべきではないと思う読者もけっこうおいでかも。いかがですか。
(2025年07月21日)