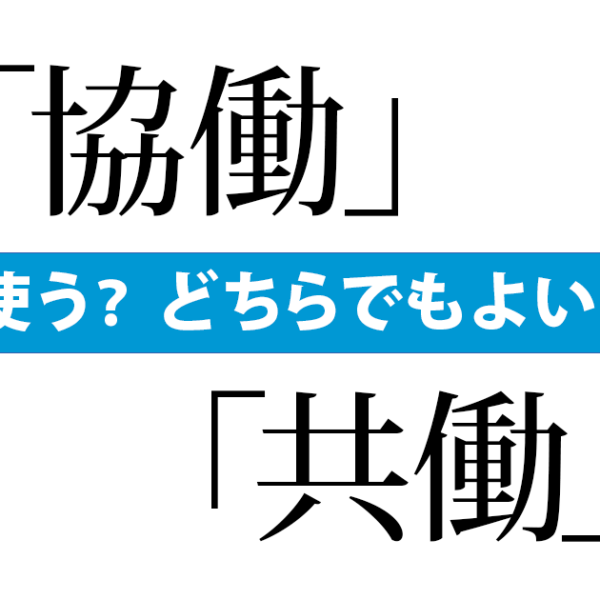「水分」を持ち歩く、という表現について伺いました。
目次
気になる人が7割を占めるが
| 熱中症の予防に「水分」を持ち歩く――カギカッコの中、いかがですか? |
| 「水分」で違和感はない 14.8% |
| 「水分補給用の飲み物」を略した形で、問題ない 16% |
| 違和感はあるが、許容できる 33.3% |
| 「水分」は成分のこと。「水」や「飲み物」がよい 35.9% |
「水分」を持ち歩くという言い回しについて、違和感や問題はないとした人は3割程度。とはいえ残りの7割のうちでも半分は許容できるとしています。実際に持ち歩く物としては水やお茶などの飲料だとしても、特に補給すべき要素としての「水分」が話題になっている場合はあまり問題視しない人が多いようです。
換喩としての「水分」
国語辞典の「水分」についての説明は「ある物の中に含まれている水や液体。また、その量。みずけ」(明鏡国語辞典3版)といったもので、これに関してはどの辞書も大差ありませんでした。水や液体そのものではなく、含有物としての水だということです。こうした説明に沿うと、水筒やペットボトルの水を指して「水分」というのも何だか気が引けます。水に水が含まれているというのはおかしく感じるからです。

ただこれは物事を文字通りに受け止めてしまうせいかもしれません。「水分」という言葉で「水分を含む飲み物」「水分を補給するための飲み物」を指していると考えればおかしいということはなくなります。「鍋を食べる」といって鍋を囲んで料理を食べ、「お茶でも飲もうか」といって実際に飲むのはコーヒーでもフラペチーノでも何とも思わないのが普通です。私たちは「水分」という言葉を、「水分を含む飲み物」の換喩(メトニミー)として使っているのだと考えられます。
「成分」を強調する場合も
とある企業のウェブサイトには「熱中症対策に、水分とミネラルを持ち歩き」と書いてありました。「水分」だけでなく、「水分とミネラル」「水分と塩分」などとあると、違和感は小さくなるように思います。水以外のものと併記することで、補給すべき成分としての水である、という点が強調されるのかもしれません。こうしたフレーズにまで注文を付けるのは余計なお世話だろうと感じます。
ただし「飲む」には合わないか
今回の質問のきっかけになった文章は「水分を持ち歩き、喉が渇いていなくてもこまめに飲む」というものでした。うーん、ここまでは「水分」を持ち歩く、でもいいじゃないかという調子で話を進めてきたのですが、改めて見ても、新聞に載せるならもう少し違う書き方をしようかなと思います。
厚生労働省のリーフレットには「室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給しましょう」と書かれています。これは違和感もなく分かりやすい書き方です。こうしてみると、単に「持ち歩く」だけでなく「飲む」まで含めて、「水分」とのなじみ具合を伺うべきだったかもしれません。「水分」には「飲む」よりも、「取る」や「補給する」がしっくりきます。
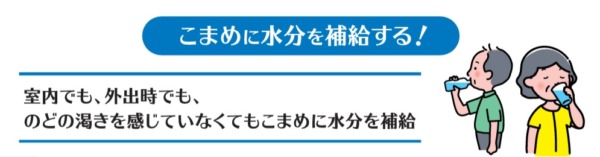
厚生労働省のリーフレット「熱中症予防のために」から
今回直した文も、メッセージは明確なのですが、文としては何だかチグハグになってしまった観があります。意味が通じるという点では間違いとはいえないものでしたが、文の完成度を意識するならば、述語と適切に呼応する言葉を選ぶ必要がありそうです。
(2025年07月14日)
例年より早く猛暑が到来。熱中症が心配されますが、予防を呼びかける原稿の中で「水分を持ち歩き、こまめに飲む」というくだりを目にしました。とりあえず「水などを~」と直すことで出稿側と調整しましたが、「水分を~」でも違和感を持たない人が多いだろうか、と気になりました。
「水分」は文字通りに受け止めれば「成分・含有物としての水。みずけ」(岩波国語辞典8版)。すなわち何かに含まれているものとしての水なので、それ自体を持ち歩くというのは何だか変な感じがします。もちろん、飲み物を持ち歩いているならそこに水分は含まれており、遠回しながら水分を持ち歩いていることにはなりますが。
しかしそれなら最初から「水」や「飲み物」と書けばよいのではないか、と直すことにしたものですが、こと熱中症を取り上げるに当たっては、体の水分を補給するためのものということで「水分」と書くのも分かりやすい書き方なのだろうか、などと後になって考えました。皆さんはどう感じるでしょうか。
(2025年06月30日)