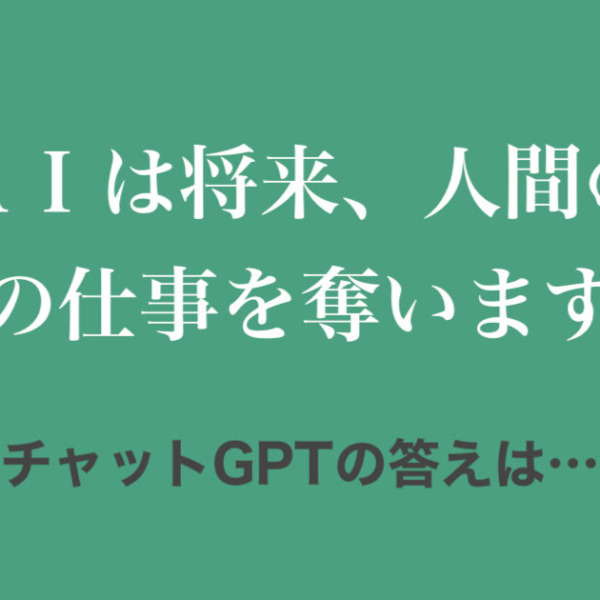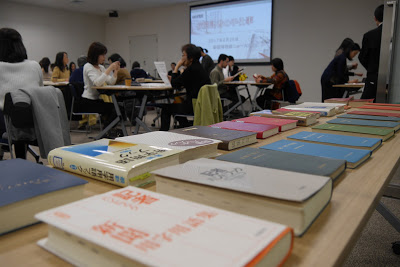漫画・アニメの「呪術廻戦」で「赫鱗」という漢字に「せきりん」と読ませています。これは正しいのでしょうか。別のアニメや映画、戦時中の新聞など、個人的な関心領域を展開させた末に到達した結論とは?

いささか旧聞に属しますが、同僚が「コラムのネタになるかと」と、こんな情報をくれました。
〈先日家で子供が見ていた呪術廻戦というアニメで、「赫鱗」という回があって「せきりん」と読ませていました。漢和辞典を見ると赫の読みは「かく、きゃく」しか挙げられておらず「せき」はありませんでした〉
目次
「赫奕姫」何と読む?
「呪術廻戦」は私の関心領域外なのでスルーしていましたが、スーパー銭湯にコミックスが置いてあったので探すと、
赫鱗躍動・載(せきりんやくどう・サイ)!!
という文字が見つかりました。
これも気持ち悪そう系で私の守備範囲外ですが、「東京喰種(トーキョーグール)」という漫画では「赫」の字が多く使われていて、これは「かく」のようです。
例えば「新潮日本語漢字辞典」を引くと、読みは漢音カク、呉音キャク、訓「あか・あかい・かがやく・かっと(くわつと・かつと)」となっていて、セキはありません。意味としては「あか・あかい」「かがやく」「かっと(怒るさま)」「おどす」などが挙げられています。
ちなみに同辞典には【赫奕姫】という語がありますが、何と読むかお分かりでしょうか。
赫奕という文字には見覚えがあります。若い頃見ていた「装甲騎兵ボトムズ」というテレビアニメの後日談のOVA(死語?)が「赫奕たる異端」というタイトルで、「かくやく」と読ませています。「奕」の方はヤクのほかエキの読みもあり、広辞苑は「かくえき」を見出し語に取り「ひかりかがやくさま。かくやく」としています。
では「赫奕姫」とは。竹取物語のヒロイン、そう、「かぐやひめ」です。輝くという意味が「赫」にあり、その連想からの当て字でしょう。広辞苑では【かぐや姫】と平仮名で掲げ、赫奕姫は一般的な表記ではないことがうかがえます。
「赫々たる戦果」戦時に多用
さて、かぐや姫は8月15日に月の世界に帰ります。もちろん旧暦の話ですが、新暦の8月15日は言わずと知れた終戦の日。今年は戦後80年ということで、毎日小学生新聞で毎日「80年前の今日 何があった?」という連載があるなど、戦争中の毎日新聞を調べる機会が増えました。
1942年8月15日、毎日新聞の前身の東京日日新聞に「赫々」は大見出しで使われていました。いわゆる第1次ソロモン海戦で、日本の勝利ではあるものの、戦果については事実と異なり、大本営発表が誇大になる端緒となったようです。

その後もことあるごとに「赫々」の見出しは使われていましたが、45年になると戦況ではなく個人や部隊の戦果をたたえる見出しに変わり、大きさも控えめになっています。翼賛記事といえども、もはや誇大に報じるべき戦果さえほぼなくなったことがうかがえます。
そして敗戦。45年8月21日、疎開先の岡山で永井荷風は「断腸亭日乗」に記します。
残暑の日光焦土に赫々(かくかく)たるのみにて通行人数(かぞう)るばかりなり。
この使い方は「輝かしい」という価値判断とは無縁で、「ひでりで燃えるように暑いさま」(全訳漢辞海)です。勝手な解釈かもしれませんが、戦時中も軍部への憎しみを日記につづった荷風がそれとは異なる意味で使い、ちょっとした反骨精神を示しているような気がしました。
往年のポルノ映画の原作は
それはともかく、「赫」という字で思い出したことがもう一つあります。日活ロマンポルノ「赫い髪の女」(1979年)です。私は見た記憶がないのですが、もしかしたら高名な神代(くましろ)辰巳監督作品だからと見て忘れているだけかもしれません。
この映画の原作は中上健次の短編「赫髪」(78年)です。たぶん造語ですが、中上健次全集2巻にはルビがついていないので何と読ませるのか分かりません。作中ずっと「赤い髪の女」とあるのですが最後の1行だけ
赫い髪は美しい。
とあります。無機質なセックス描写が続いた果てに最後だけ唐突に出てくる「赫」。主人公の男にとって単なる赤ではなく輝くように思えたのでしょうか。それとも、新潮日本語漢字辞典で「血や炎の色」とあるように、なにかまがまがしい予感を抱いたのでしょうか。
作家の意図は分かりませんが、いずれにせよ単なる「赤」だけでは表現できないとして、題名にも「赫」が使われたのは間違いありません。
漢和辞典をさらに調べると…
さて、脇道が長くなりました。「呪術廻戦」で「赫」が使われたのは、単なる「赤」を超える強い技という意味合いを持たせたと思われます。そして漢字辞典の記述を知ってか知らでか、「血の色」というイメージと結果的にリンクしているようです。しかし「せき」というルビ、これは適切なのでしょうか。
実は諸橋轍次「大漢和辞典」や白川静「字通」などにはセキの読みがあるのです。「字通」によると、「カク セキ あかい」の三つの読みがあります。熟語として挙げられるのはカクばかりだし、小型漢和辞典にはセキは見当たらないのですが、その読みも間違いとはいえないことになります。
答えだけなら数行で済むところを長々と失礼しました。確かにコラムのネタにさせてもらいました。
【岩佐義樹】