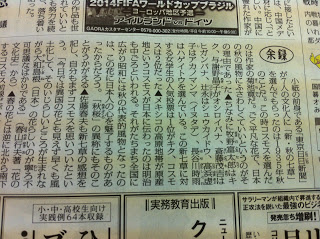読めますか? テーマは〈酒食用具〉です。

蝶漆絵根来瓶子(メトロポリタン美術館)
目次
卓袱台
ちゃぶだい
(正解率 94%)食事用の台のこと。脚は短く、折り畳みできることが多い。「ちゃぶ」は茶飯の中国音chafan、あるいは中国風の食卓「卓袱」(卓袱=しっぽく=料理として長崎に伝わる)のchofuからきたという。また一説に、食事のことを「ちゃぶちゃぶ」といったことからとも。なお「ちゃぶ台をひっくり返す」という表現を見ることがある。漫画・アニメ「巨人の星」からきた新しい慣用句となるかもしれない。
(2011年11月07日)
選択肢と割合
| たたきだい | 2% |
| たっぷだい | 4% |
| ちゃぶだい | 94% |
備長炭
びんちょうずみ
(正解率 55%)「びんちょうたん」ともいう。熊野産の良質の木炭。元禄年間の商人、備中屋(びっちゅうや)長左衛門が広めた。その名に基づく命名という。現代でも焼き鳥屋やウナギ屋などで用いられるブランド品である。
(2011年11月08日)
選択肢と割合
| そなえながずみ | 0% |
| びちょうたん | 44% |
| びんちょうずみ | 55% |
利久箸
りきゅうばし
(正解率 85%)利休箸とも書く。中央を太く、両端を細く削った箸。千利休が考案したといわれる。「利久」は「利を休む」との意を嫌って「利が久しい」と字を替えたとか。箸は2010年採用の常用漢字。
(2011年11月09日)
選択肢と割合
| としひさばし | 1% |
| りきゅうばし | 85% |
| りくばし | 14% |
行平鍋
ゆきひらなべ
(正解率 91%)「雪平鍋」とも書く。取っ手や注ぎ口の付いた鍋。平安時代の歌人、在原行平(「伊勢物語」で有名な在原業平の兄)が、須磨に流された際、海女に潮をくませて塩を焼いたという故事に基づく。鍋は2010年採用の常用漢字。
(2011年11月10日)
選択肢と割合
| ぎょうへいなべ | 5% |
| こうへいなべ | 3% |
| ゆきひらなべ | 91% |
瓶子
へいし
(正解率 66%)「へいじ」ともいう。酒を注ぐための容器。口と下部が狭く上部が膨らんだ、とっくりのようなもの。鹿ケ谷(ししがたに)で平家打倒の談合をする人々が、瓶子が倒れたことで「平氏が倒れた」と喜んだという。「平家物語」が伝える古典的おやじギャグだ。
(2011年11月11日)
選択肢と割合
| さじ | 25% |
| びんご | 9% |
| へいし | 66% |